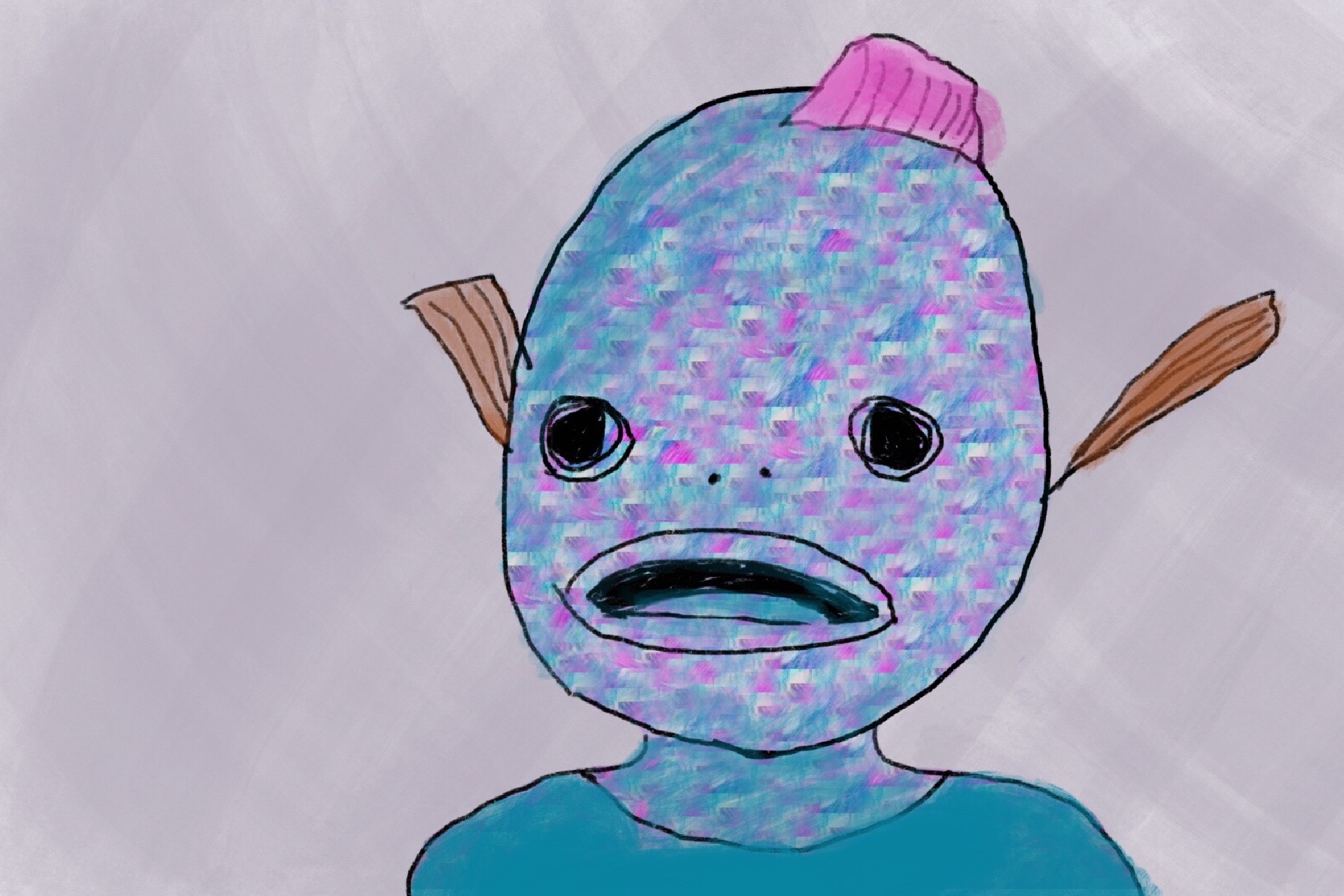展示作品一覧
Sweetdream
Fumina Otaki
イメージラボ / 写真
写真を撮る上での平面的な空間に面白さを感じ、写真にアナログ的何かを加えた作品を中心に制作。
3年生の後期から食品をテーマにした作品を制作しており、人物写真を撮影し印刷後に直に食品を重ねて撮影する手法をとり、空間的な面白さや食品と美の形を表現した。
変心
山本 桂子
フューチャーラボ / インスタレーション
子供の時は、遊園地のアトラクションに入っても仕組みのことはほとんど考えずにアトラクションの内容に対して純粋に向き合っていた。
大人になってからは、アトラクションの本質的な面白さや怖さよりは仕組みなどの方が気になるようになった。
しかし、どちらも作品を楽しんでいることには変わりない。
この視点の違いはアート作品にも通じるところがあると感じたため、この差異をお化け屋敷を舞台にした複数の媒体で、動きがリンクするアニメーションで表現する。
postposter
國久 頌竜
イメージラボ / 平面 半立体
ポスターはもう不要かもしれない。
近年のWeb広告やデジタルサイネージなどの台頭により、アナログ広告としてのポスターの価値は失われつつある。
これまでポスターは文字、図像、色という要素で構成されてきた。
これからはここに、物質という新たな要素を提案したい。触って肌で感じる、しかけを通して遊ぶ、などのように、デジタルにはない物質性こそが、この先ポスターが生き残る術なのではないだろうか。
ポスターの次のメディアはデジタルか、それとも。
ねこのスープ
橋浦 紀乃
メディアラボ / かるた 立体
体調が悪いときや食べることすら面倒に感じたとき、自分がよく食べていたのはスープだった。
調理の手軽さ故に様々なアレンジ方法が生まれ、その土地ならではの具材や歴史的背景を持つものも誕生した。
遊びを通してスープを知り、歴史を知り、実際に作ってみる。
本作品はそんなスープを題材にした食育かるたである。
ふなかたんまちプロジェクト
スズキ サオリ
フューチャーラボ / 立体
このプロジェクトは、私の地元の“祭り”に限定した独自の広報活動である。
日本の“祭り”は、約1300年にもなる長い歴史を持つ伝統文化だ。
私の地元、千葉県館山市でもその文化は今でも色濃く継承されてきた。
祭りの内容は伝統そのもので、通常不変の存在であるが、時代性に合わせて少しずつ変化していることに気がついた。
祭りには決まった“衣装”が存在しているが、最近では衣装そのものの型は崩さず、オリジナリティに富んだ自作の衣装を着用する者が現れた。
本作では変化する“祭りの衣装”にスポットを当て、今までオリジナルが存在しなかった足袋に独自の文化性を取り入れた“祭りのための足袋”を、地区の数だけ制作した。
この作品を観て、少しでも古き良き祭り文化に興味を向けて貰えれば幸いだ。
HALLOWTIDE MAGIC
天上院 リュウ
イメージラボ / 映像 立体
「人は何にでもなれる・なることができる」をテーマに、悪霊から身を守るべく仲間だと思わせるための“仮装”文化を持つハロウィンの祝祭を題材にした。
楽曲制作・出演・アニメーション制作など、全てを自分一人で行った自作自演のミュージックビデオ。
Drummer's Face Synthesizer
佐野 仁崇
メディアラボ / パフォーマンス
私は今回、ドラムのように感覚的に演奏できる楽器とその形態の制作を目指した。
私はドラムの魅力の一つとして、そのとっつきやすさが挙げられると考えている。しかし、ドラム単体での演奏はそれなりの技量が求められるものだ。
そこで私は、ドラムを叩きながら演奏でき、ドラマーが圧倒的なスキルを持ち得なくても、一人で演奏できる形態のひとつとして今回の作品を提案する。
show女
なまず丼
メディアラボ / 立体
アニメを年代問わず自由に見られる現代において、アニメのような線、色合いで描かれた少女や少年のイラストは公的性を含んだ理想を表ている。
しかし、それは同時に現代に生きる我々を含んでいる。
完璧な少女や少年のイラストがいびつに歪む姿や、外見の可愛さにそぐわない行為が描かれた作品は、理想と現実との差を表し、そこから私たちが何を感じて生きているかを知れる。
私は本作で、そのようなアニメ的イラストを身の回りにある様々な物体に描き、理想と現実のギャップやその有無の顕在化を試みた。
あなたは誰かの大切な人
工藤 朝咲
フューチャーラボ / 写真
決して自分や人のことを責めないであげてほしい。
人に不快にされた時、思い出してほしいのが自分の大切な人のことだ。
私はその人がどんな人か知っているからこそ大切にできている気がする。
それと同じで、どんなに反りが合わない人がいても、その人にも大切な人がいるはずだ。
同じように、あなたが嫌われたりあなたが自分を許せなくても、あなたを大切に思っている人が絶対にいる。
この作品は私の家族の祖父、母、兄や私の人生を時系列に表している。
誰にでも大切な人がいること、あなた自身が誰かの大切な人であることを思い出してくれたら嬉しい。
めぐる香り
木村 紗妃
メディアラボ / インスタレーション
香りは、衛生、医療、儀式、食、ファッションなど様々な領域と結びついてきた歴史を持つ。
それは嗅覚が人の感情に強く働きかけるからだ。ふとした瞬間に風とともに運ばれてやってきた香りが、忘れていたはずの記憶を呼び起こした経験があるだろうか。
私は懐かしい香りに出会ったとき、頭の中を映像が駆け巡る感覚を覚える。
しかし、嗅覚は視覚などの感覚に比べて常に意識されることはない。
何もない状態で意識的に香りを嗅ごうとすることはほとんどないだろう。
だからといって、香りが私たちに必要無い訳ではない。
この展示では香りが人にとってどのように扱われてきたのかを紹介し、インスタレーションを通して香りとの新たな向き合い方を考える。
PIMPLE___〈思春期によせて〉
清水 咲希
メディアラボ / 刺繍
昆虫が蛹に、あるいは脱皮を繰り返し成虫へと形を変えるように、人間は「思春期」という期間を通して肉体的、精神的に変化していく。
本作では、思春期特有の身体的特徴であり、成長における皮脂の過剰分泌が原因となるニキビをモチーフに選んだ。
「ニキビは隠すもの」という考えとは逆に、ニキビは思春期の皮膚に現れる“装飾”だと考え、布に装飾をする際に使われる手法である刺繍を用いてニキビを表現した。
愛される為に。
酒井夢加
フューチャー / 立体
虐待や両親の不仲など歪んだ家庭で育ち、親から適切な愛情を受けられないまま大人になった人々をアダルトチルドレンと呼ぶ。
アダルトチルドレンたちが抱える精神的な歪みやトラウマから、様々な形で現れる「愛されたい」という想いを、一部の自嘲を込めたアダルトチルドレンの言葉に従って「心に巣食う化け物」の形で表現した。
I'm here.
小林 優希
イメージラボ / 写真
「全てのものは確かに意味を持って存在している」
私たちの身の回りはたくさんの「モノ」で溢れている。
それは大小様々存在し、当たり前のように私たちの生活に根付き、当たり前のように消費されている。
そういった存在を作品として昇華することで身近にある「当たり前」を見直し、日々の生活の豊かさに気づく。
そして自分自身が画面に加わることで私が存在することを知る。
この作品の鑑賞者が身の回りの小さな存在に気づき、意識を向けるきっかけになればと思う。
People Gaming People
NOCUTAN
メディアラボ / 立体インスタレーション
この作品は、ゲーム依存症になった経験からゲームと身体の関係について思考したものだ。
人々には現実でも有意義なゲーミングライフを送っていただきたい。 自身は、ゲームを体験している状態の身体や習慣を表現として捉え、双方の体験をエンパワーさせる作品を展開させていく。
still alive
ダーヤマ 佰彩
フューチャーラボ / 半立体
"文明の発達により何でも手に入れることができる現代社会だが、実は一番求められているのは少女の姿に象徴される無垢な健康ではないだろうか。
お金を出しても叶わないが、それがサプリメントや薬に支えられているとしたら。そんな薬の光と影を、少女の絵と薬のシートを用いて表現した。
一見この作品は、キラキラとした薬のシートの美しさに目を奪われるだろう。しかしそこには、かつて大量の薬が存在していた残骸も垣間見える。ただ美しいと感じるか、同時に恐怖も覚えるか。それは、鑑賞者の人生に薬がどのようにして関わってきたかによって変化するだろう。"
シュレッダーマン ヒュー(マン)
李杏
メディアラボ / 小説
①シュレッダーマン
物語と読者間に生じる認識のズレを、地の文とキャラクター、本文とルビ、物質と情報、人類と世界へと落とし込んだエンタメ小説
現実世界でも生じる失認を、小説というメディウムで再現し、それを利用して物語は進んでいく。読者は、この映像化不可な文学作品を脳内で映像化しながら、マクロでどこか無責任な終末劇を体感することになる。
②ヒュー(マン)
全ての人は産まれながら平等に獣を飼う。
物語が少しずつ〈改善〉されていく、アップデート型小説。"
あなたとわたしの惑星名
小野花織
イメージラボ / 映像インスタレーション
"再生される。
「人間は星の一部だ。」
なんだかもうずっと頭から離れない。
ぐるぐる、ぐるぐる、まわってる。
地球が重力で人間を引きよせているとき、人間も地球を引いているらしい。
分離した地球の私たちは、ずっと引かれている。
分離した地球の私たちが、ずっと引いている。
いつか合わさり地球に還る。
私たちはひとつの存在になった。"
愛💟コンタクト 〜宇宙との交信👽〜
碧音
イメージラボ / 映像インスタレーション
扇風機で一度は宇宙人のマネをしたことがあると思う。
そして、扇風機がここから何億光年先の星に住む宇宙人とコミュニケーションが取れる装置になったら面白い、そんな思いつきから制作した。
宇宙人はある人間と心を通わせるためにこの装置を作り、言葉の代わりにソルレソル(音楽言語)を用いて会話を成立させようと試みている。
会場内には扇風機の回る音、扇風機でインタラクティブに震えている歌声が響き渡り、宇宙人は懸命にこちらにダンスを披露する。
Images
ちゅら
メディアラボ / 絵画
何かを描写する時、画面の上で時間をかけながら完成させていくその絵は、本当にその時見たものを描写できているのだろうか。
風景を描こうとすれば空の色や雲の流れが変わっていき、“その時見た風景”とは違う風景を見ながら描き進めていくことになる。
“その時見た風景”を描き起こそうとしたとき、どんな絵になるのだろうか。
sound(raw)ing
吉岡 雄大
メディアラボ / パフォーマンス
塗料を出す自作楽器を複数用いてひとつの絵を描くパフォーマンス作品。
作家はこのパフォーマンスの中で「ドローイングに規定されるサウンドパフォーマンス」と「サウンドに規定されるライブドローイング」を繰り返し横断する。
ロボットは作家とともに絵を描き、音を鳴らす。
恥を知る滅び方について
昭理(SoLy)
メディアラボ / インスタレーション
2020年には月に人が住めると想像していた。
私たちは、経済は成長すること、問題は解決すること、全ては発展することだと考えた。
全く新しく素晴らしい何かの技術が全てを一気に解決してくれるはずと、その真ん中にテクノロジーという神を作り上げた。
完璧でなければ意味などない。
2022年の私は地球に人の滅亡を実感した
現代という無機の構造の中に生き残っている有機の生き方がある。
伝承されてない空白は儀礼と信仰によって埋められる。
その儀礼と信仰を遡り、無機と有機を逆転する。
恥を知る滅亡を迎えるために。
原始的な/映像/に関する実践
檜村 さくら
メディアラボ / 映像インスタレーション
この作品郡は、映像を構成している最小単位の要素を拾い上げることによって、映像の中にある「空間」について再考し、現実空間を映像メディアに収めることの意味を捉えようとする、4つの試みだ。
①《イメージのための構造体 The Structure Consecrated to View》
鏡や光に作用する素材を用いて、映像を発生させるために作られた構造物、及びそれを使って撮影した映像。
②《世界の約分の世界 World Reduction of A World》
自宅で、カメラのスイッチングを行う装置と日用品を使って画面構成をいじり「編集」を行なうパフォーマンスの記録映像。
③《紙の上を歩く Walk on Paper》
一枚の紙の上に書いた文字や落書きを接写でカメラが追い、それを読み上げたものを「詩」とする映像作品。
④《イメージのための空間(習作) The Space for View(Study for a Piece)》
3D空間上で作られた「映像として見るための建築物」をバーチャルで歩く映像。
これらの試みによって私は、映像とそれを撮影する実空間の密接な関わりについて明らかにすることで、映像という表現媒体が行なっている世界の再創造という行為についてその不確かさを明らかにするとともに、
実空間世界というものそのもののあやふやさ、そして現実への“想像の世界”の入り込む余地について再提示しようと思う。
私が作家として常に持っているテーマ「入れ子構造」は、ビデオインスタレーションという表現手法を用いて既存の概念の転換可能性とダイナミズムを追求するものだ。
この四年間は、映像を撮るという状況の再演やフィクションのメタ構造をテーマにした作品を通して、嘘と本当、虚構と実像、想像と現実のあわいに現れるゆらぎを表現してきた。
この作品で行なっている物理的な操作で映像世界を作り出す営みは、あらゆる人にとって映像制作が一般的となった今、も基本的な映像演出技法としても知られている。
この作品ではその営みをよりミクロな範囲で追尾することで、アイロニカルに想像と現実の概念のマクロな転換可能性を表現し「入れ子構造」に言及しようとしている。
「☆¿※◉♯」が私を擬物化すると
古山 寧々
メディアラボ / インスタレーション
私が「パソコン」と関わるとき、私は指でキーボードに触れる。
このとき「パソコン」からすれば、私という人間は指だけの存在となるのだろうか。
あるモノにとって、私がどのような姿・動きをするのかは、そのモノと私の関係性によって随分異なるだろう。
私は普段過ごす部屋にある「モノ」が私を擬物化すると、どうなるのかを考えてみた。
擬物化というのは、擬人化(非人間を人間基準で見立てること)の逆、つまり人間を非人間基準で見立てることである。
人間基準の知覚に画一化された擬人化に対し、擬物化された人間はヘンテコなのだ。
映像作品一覧
TRAUMA
彩り
イメージラボ / 映像
人は簡単に死ぬということ。
無知な優しさは、
時に人を殺す恐ろしさを秘めているということ。
私がそれを知ったのは、
3年前の梅雨の候だった。
わたしたちのいるところ
天田理紗
イメージラボ / 映像
成長に伴う痛みを、無かったことにするのは難しい。
それでも、古い自分を切り捨てながら、私は新しい居場所へと飛び立つ。
ささやかな日常
絵塚るこん
フューチャーラボ / 映像
この作品は、何気ない日常に潜む、あるいは気付きづらいけれど確かに存在している「幸せ」を、ある一人の大学生の日常をモチーフに描いたアニメーションだ。
この作品には明確な起承転結といった展開は無く、ただ平凡な日常のシーンを切り取っただけに見えるかもしれないが、その中には鑑賞者自身で無意識にその「幸せ」を感じ取って欲しい、という思いを込めた。
すくい
池永菖香
フューチャーラボ / 映像
私を救って、
私を許してくれる人は、
私しかいないのだ。
ゆらら
くまがいらら
フューチャーラボ / 映像
呼吸は生きていることがわかるひとつの指標である。
アニメーションの1コマ毎の描写の濃度や描き方を変化させることで「呼吸」を描いた。アニメーションは1コマ1コマは静止画なのに、それらが繋がると命を宿したように動き出す。それは対象物の生きている様子を一瞬も逃さず常に追っているように感じる。
この赤ん坊は昼寝をして夢を見ている。
人の赤ん坊には祖先の記憶の名残があるという。この赤ん坊が見ている夢の中で、私たちの祖先との繋がりやこの地球にいる生き物との繋がりを「呼吸」という共通の生理現象を通して描いている。
How to become a Mermaid
栗田佳奈香
イメージラボ / 映像
人魚になりたかった中年の男。彼は外の世界と家族に疲れ、逃げるが、それすらも不可能であるように感じていた。彼はしきりに人魚になる薬を打ち続けていく。何かから逃げるように、ずっと。一方で彼の娘は父親の様子にも外の世界にもうんざりしていた。
この女は全てが嫌だった。この女は自分は無だと感じ、生きながら死んでいる。しかし今度はその状況にも疲れていく。悲しみや虚しさに飽きている。
次にとるべき行動は何か考えたりしてみた。
かんがえてもわからなかった。でも、あたらしい衝動がふいにでてくる。
突然それにあたった。とつぜんに。あるひ。
Monster Memory
503-Wakingyo
フューチャーラボ / 映像
僕は人と話すとき、
なるべく先入観を持たないようにしているつもりだ。
だが、境遇であったり常識がそもそも違っていたり、
自分が過去に経験したことから勝手に想像して
押し付けてしまうことがあった。
この映像はそういった出来事から出発している。
コップの海
148
イメージラボ / 映像
答えのない問題にぶつかった時、あなたはどうする?
どう足掻いても自分ではどうすることもできない問題にぶつかった時、
私は「わからない事を、わからないままにする」のも大切だと感じている。
誠実に向き合った結果が「わからない」ならば、
わからない曖昧なままで向き合いたいと私は思うのだ。
そして、この際限の無いわからなさは、どこか希望のようなものであると私は感じている。
このような問題にぶつかった時、
私は自身の中にある苦しみや悲しみ、喜びや小さな気付きが、
他者を越えた、何か大いなるものへと繋がっているような気がするのだ。
不透明な壁
白榊快理
イメージラボ / 映像
テーマは『LGBTQ+』。
抑圧され続けている若いLGBTQ+の人たちを題材に制作した。
「性的マイノリティの人には共感できない」ことの否定と、家族・社会の中での生き辛さを表現した映画である。
少しでも差別や偏見が無くなり、生きやすい世の中になることを願う。